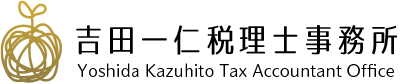新型コロナウイルス感染症に関連する各種情報

2019年12月から中国・武漢で流行しだした新型コロナウイルスによる感染症は、日本や韓国をはじめ、世界中の国に波及しています。
そして、2020年に入り、全世界で新型コロナウイルスによる感染症が猛威をふるっています。もちろん、日本も例外ではありません。
特に、2020年4月6日に出された緊急事態宣言の対象区域となった東京・大阪などの大都市およびその周辺地域では、多くの店舗が休業・短縮営業に追い込まれるなど、経済活動にも深刻な影響が及んでいます。
新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっていることで、日本も含めた世界中の経済情勢が著しく悪化しています。
日本だけを見ても、飲食店など「実際に店舗に来てもらい、商品・サービスを提供すること」が前提の業種は、特に深刻な打撃を受けているのが現状です。
そこで本記事では、新型コロナウイルス感染症に関連する様々な記事を解説します。
目次
従業員に見舞金や手当を支給した場合の税法上の扱い
見舞金が非課税所得になる条件は?
「コロナの大変な状況で頑張って仕事をしてくれたのだから、少ないけど見舞金や手当をあげたい」と思った場合は、併せて税法上の扱いについても確認しておきましょう。
新型コロナウイルス感染症の流行によって発生する取引についての税法上の扱いは、国税庁が「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」として取りまとめています。
その中には、見舞金が非課税所得になる条件として、以下の3つが掲げられています。
- その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
- その見舞金の支給額が社会通念上相当であること
- その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと
エッセンシャルワーカーや感染してしまった人なら非課税になる可能性が高い
それぞれの条件について、確認してみましょう。
まず、2については、社内の慶弔規程等や過去の取扱いに照らして相当であれば大丈夫です。
また、3については、支給額が通常の給料を基準に決定される場合は当てはまらないなど、一定の条件があるので注意してください。
最も慎重に考えるべきなのは、1でしょう。
従業員等やその親族が新型コロナウイルス感染症に感染した時に出すお見舞金では、非課税所得になる可能性が高いです。
また、たとえ従業員本人や家族が感染していなかったとしても、以下のような不特定多数の人と接さざるを得ない仕事に従事していた場合も、手当が非課税所得になる可能性は高いです。
- 医師、看護師、介護士などの医療関係者
- スーパー・コンビニ・薬局の店員
- バスや電車の運転手 など
逆に、不特定多数の人と接することがない仕事に従事していた従業員に対して、新型コロナウイルス感染症を理由に手当を支給したとしても、それは給料の一部として課税される可能性が高いです。
具体的にどう判断すべきか、個々のケースによって結論が異なるので、税理士などの専門家や税務署に確認してみましょう。
休業せざるを得ない事態で従業員に給料は支払わないといけないのか?(休業補償)
休業した場合の給料の扱いはどうするべきか
新型コロナウイルスの影響により経済活動にも深刻な影響が及んでいる中、扱いに慎重な判断が求められるのが、「企業が休業している間の従業員への給料」です。
休業や短縮営業に踏み切った場合、平常時のような売上は見込めません。
しかし、「売上がないから給料も0」というのは、従業員に過大な負担を強いることになります。
実際のところ、休業した場合の従業員への給料補償の必要性については、「休業の理由」によって扱いに差があるので注意が必要です。
この点について法律ではどのように定めているのか、まずは扱いを確認しましょう。
原因が何かによって扱いが異なる
休業の理由を大きく分けると、以下の3つに分かれます。
①企業に故意・過失がある場合(例:不当解雇)
②企業の経営・管理上の障害があった場合(例:機械・設備の故障)
③天災事変(例:地震、原子力発電所の事故)による不可抗力であって、企業の責めに帰することができない場合
①の場合、労働者である従業員に対し、平均賃金の100%を支払わなくてはいけません。
しかし、労働者に懲戒事由がある(例:事件を起こした)など、一定の条件に当てはまる場合は、就業規則に扱いを定めることで、給付の額を切り下げることができます。
②の場合は、企業は従業員に対し、平均賃金の60%を支払わなくてはいけません。
ただし、就業規則に「休業時は平均賃金の80%を支払う」など、別途規定があった場合は、高い方の金額を優先します。
そして、③の場合は「企業のせいではない」以上、休業補償を行う義務はありません。
今回の新型コロナウイルスによる感染症が、どこに当てはまるのかについては、これから説明しましょう。
不可抗力の判断基準とは
新型コロナウイルス感染症の流行およびそれに伴う緊急事態宣言の発令により、自身の事業を休業するかどうかの判断を迫られた事業主の方は多いはずです。
そこで、新型コロナウイルス感染症による休業について、従業員への責任はどこまで負うべきかについて考えましょう。
まず、新型コロナウイルス感染症の流行は、事業主の故意・過失によるものではありません。そのため、平均賃金の100%を支払う必要はないでしょう。
そこで、実際に休業補償について考えるとしたら、「企業の経営・管理上の障害があった場合」になるのか、「天災事変による不可抗力」になるのかの2択で考えることになります。
ここで、新型コロナウイルス感染症の流行が「不可抗力」になるのかについてですが、2011年に発生した東日本大震災の際に、厚生労働省は「不可抗力」として認められる条件を定めました。
雇用調整助成金も上手に使おう
具体的には、以下の2点が認められれば「不可抗力」として認められます。
- その原因が事業の外部より発生した事故であること
- 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
今回の新型コロナウイルス感染症の流行について、これが「不可抗力」と認める公式な見解はまだありません。
しかし、感染症の流行は事業とは関係なく起こり、1企業の力で回避できものではない以上、「不可抗力」に該当する可能性は高いです。
そのため、本来であれば休業補償を行う必要はないと考えられます。
ただ、従業員の命と生活を守るため最大限の配慮をするのは、事業主としての責務です。
今回の新型コロナウイルス感染症の流行による休業に対し、厚生労働省は雇用調整助成金の適用条件の緩和を発表しています。
簡単にいうと、休業補償を支払う事業主に対し援助を行うということです。
このような制度もフル活用し、なるべく休業補償を払うようにしましょう。
資金繰りが厳しいなら、税金の支払いを猶予してもらう
新型コロナウイルス感染症による納税の猶予とは
首相官邸は2020年3月18日に「生活不安に対応するための緊急措置」(以下、緊急措置)を発表しました。
緊急措置の中では、以下の4つを柱とし、関係各所への要請が行われる旨が明らかにされています。
- 個人向け緊急小口資金等の特例の拡大
- 公共料金の支払いの猶予等
- 国税・社会保険料の納付の猶予等
- 地方税の徴収の猶予等
そして、緊急措置を受け、国税庁は納税・換価の猶予を行うことを明らかにしました。
まずは税理士・最寄りの税務署に相談してみよう
納税の猶予を受けるための条件は、以下の4つです。
- 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる。
- 納税について誠実な意思を有すると認められる。
- 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がない。
- 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されている。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響で、申告所得税・贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告の期限が2020年4月16日まで延期されました。
そのため、これらの税金については納期限2020年4月16日を基準として扱い、手続きが進められる点にも注意してください。
また、納税の猶予を受けられる事情としては、自分または家族・従業員が新型コロナウイルスに感染した、旅館やレストラン・居酒屋を営んでいたが需要が一気になくなり廃業した、などが考えられます。
まずは、税理士・最寄りの税務署に相談してみましょう。
急なピンチに備えるセーフティネット保証とは?
セーフティネット保証とは
新型コロナウイルス感染症自体も大きな問題ですが、同じくらい問題なのが経済への深刻な打撃です。
日本国内に限れば、愛知県では旅館が、北海道ではコロッケ店を運営する食品会社が連鎖倒産しました。
倒産とまではいかなくても、業績の急激な悪化が懸念される会社がこれからも出てくるでしょう。
そこで、このようなケースに是非活用してほしい制度として、セーフティネット保証について紹介したいと思います。
セーフティネット保証とは、今回の新型コロナウイルスによる感染症のように、大きな経営上の困難に直面した中小企業・小規模事業者を救済するための保証制度です。
セーフティネット保証は、中小企業信用保険法に基づいて定められた制度で、経営上の困難が生じた理由により「経営安定関連保証」「危機関連保証」の2つに分けられます。
「経営安定関連保証」と「危機関連保証」
経営安定関連保証とは、取引先企業の倒産や活動制限、自然災害、不況などで経営が不安定になった事業者に対し、円滑な資金供給を行うため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度のことです。
経営が不安定になった原因別に、1号から8号まで設けられています。
今回の新型コロナウイルスによる感染症の拡大に伴い、経済産業省は4号(自然災害等の突発的災害)・5号(全国的に業況の悪化している業種)を用いた中小企業・小規模事業者への支援を行うことを表明しました。
一方、危機関連保証とは、リーマンショックや東日本大震災のように、国内外の突発的な混乱で金融情勢が悪化し、経営が困難になった中小企業・小規模事業者の救済使われる保証制度です。
いずれの保証制度も希望する場合、事業所所在地の管轄の市区町村長の認定と、金融機関と信用保証協会による審査を受ける必要があります。