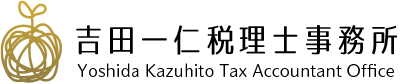税理士が教える税理士の選び方。失敗しない12のチェックリスト
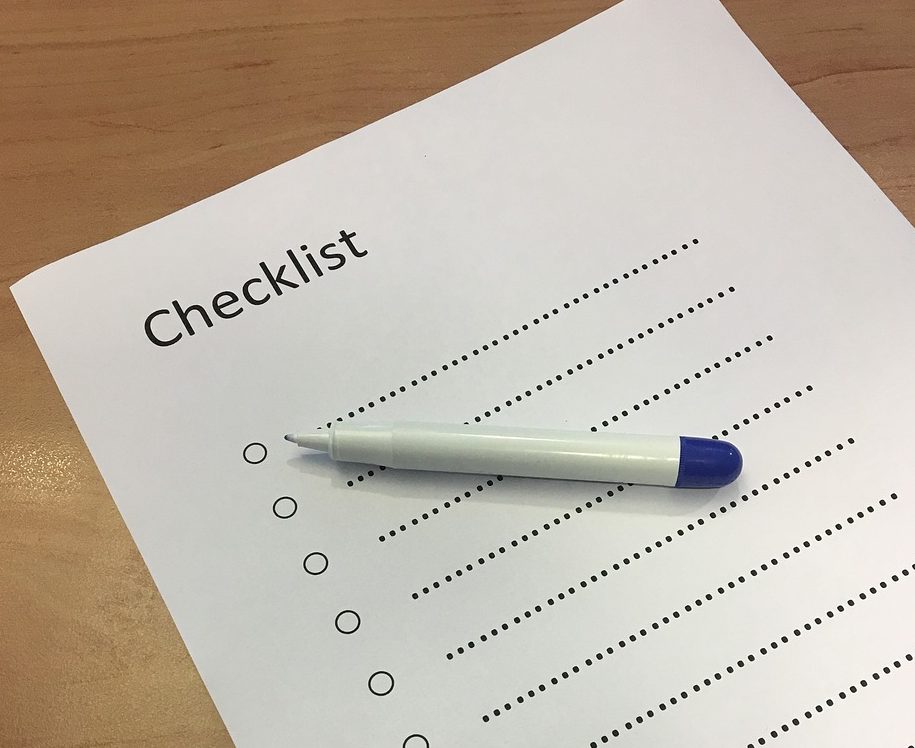
税理士選びで失敗したくない!税理士の選び方のポイントが知りたい!
個人事業主や中小企業の経営者もしくは起業を検討している方にとって、良い税理士を選ぶことはとても重要です。
なぜなら、良い税理士に出会えれば、節税はもとより経営のパートナーとしてビジネスを成功に導いてくれる可能性が高まるからです。
そこで、これまで数多くの中小企業経営者に選ばれてきた当事務所「吉田一仁税理士事務所」が、失敗しない税理士の選び方をご紹介します。
ぜひ本記事をチェックリストのように活用いただき、良い税理士を御社の経営のパートナーとして受け入れる一助としてください。
目次
- 1 良い税理士を選べば、経営が断然ラクになる
- 2 税理士選びに失敗してしまうとどうなるのか
- 3 失敗しない税理士の選び方のポイント【チェックリスト】
- 3.1 1.経営のパートナーとしての第一印象・相性はどうか
- 3.2 2.積極的に経営に関するサポートを行ってくれるか
- 3.3 3.必要な時にすぐに対応してくれるか(レスポンスの早さ)
- 3.4 4.節税について知識・経験をもとに具体的な提案をしてくれるか
- 3.5 5.顧問料・決算料など報酬料金の体系に明瞭性があるか
- 3.6 6.経営に関する相談に対して具体的にサポートしてくれるか
- 3.7 7.自社の業界・業種に関する知識や経験を有しているか
- 3.8 8.資金調達に強いか
- 3.9 9.決算対策に関して幅広い視点から提案を行ってくれるか
- 3.10 10.役員報酬の金額設定に関する相談に具体的に対応してくれるか
- 3.11 11.度重なる税制改正に追いついているか
- 3.12 12.違法性のある脱税・粉飾決算を提案してこないか
- 4 税理士を選ぶ・契約するタイミング
- 5 税理士の探し方
- 6 税理士を変更する前に押さえておくべきポイント
- 7 まとめ:失敗しないためのポイントをしっかり押さえて、自社に合った税理士選びを!
良い税理士を選べば、経営が断然ラクになる
自社に合った良い税理士を選び、きちんとした顧問契約をすることができれば、経営をラクにすることができます。
その理由や税理士と顧問契約するメリットを以下に示します。
- 節税により無駄な支出が減り、資金繰りに余裕が生まれる
- 決算や確定申告作業がラクになり、経営者に貴重な時間が生まれる
- 上記の結果、経営者が本来すべき経営に専念できる
- 対外的に社会的信用を向上できる
- 税務調査にも立ち会ってくれる
- 経営サポートを受けられることもある
税理士は税務・会計の専門家として、主に確定申告の代理や税金に関する相談業務を行います。
さらに、税理士によっては経理業務の一部を代行してくれる記帳代行・経理代行や、経営全般に関するコンサルティング業務も行うこともあります。
参考:記帳代行/お金と時間を無駄にしない経理代行/代表コンサルティング
つまり、良い税理士と顧問契約できれば、税金・会計に関する正しい知識をもとに経理代行もしてもらえたり、先に述べた節税や経営サポートといったメリットを受けられるのです。
税理士選びに失敗してしまうとどうなるのか
税理士選びに失敗してしまうと、最悪の場合にはビジネスに失敗してしまいます。
少し大げさな表現をしましたが、具体的には以下のようなコミュニケーショントラブルが多くなっています。
2017年の「会計事務所白書」によると、税理士・会計事務所と顧問契約解除した理由として次のような回答がありました。
- 代表税理士ではなく会計事務所に勤務する職員が対応のため、コミュニケーションがビジネスから程遠い
- 上から目線
- 会社に対してアドバイスがほとんどない
- 税理士資格を持っていない人が担当者になっていたので、質問の回答に時間がかかる
- IT化が遅れており、手作業が多くわかりにくい
- 節税に対する提案が少ない
- 依頼事項が数ヶ月放置された
- 事前の精査が不十分で修正申告の事態となった
このようにせっかく顧問契約した税理士でも、上記のようなコミュニケーションのずれにより、顧問契約の解除に至ることも多くあります。
このようなことにならないためにも、失敗しない税理士選びはとても重要です。
失敗しない税理士の選び方のポイント【チェックリスト】
失敗しない税理士の選び方のポイントを12点紹介します。
- 経営のパートナーとしての第一印象・相性はどうか
- 積極的に経営に関するサポートを行ってくれるか
- 必要な時にすぐに対応してくれるか(レスポンスの早さ)
- 節税について知識・経験をもとに具体的な提案をしてくれるか
- 顧問料・決算料など報酬料金の体系に明瞭性があるか
- 経営に関する相談に対して具体的にサポートしてくれるか
- 自社の業界・業種に関する知識や経験を有しているか
- 資金調達に強いか
- 決算対策に関して幅広い視点から提案を行ってくれるか
- 役員報酬の金額設定に関する相談に具体的に対応してくれるか
- 度重なる税制改正に追いついているか
- 違法性のある脱税・粉飾決算を提案してこないか
1.経営のパートナーとしての第一印象・相性はどうか
パートナーは「共同で仕事をする相手」といった意味を持ちます。
前述のとおり、税理士は中小企業経営と関係が深い経理業務・財務業務やコンサルタント業務を担います。
そのため、税理士は中小企業の経営者にとって最も身近なパートナーとなります。
経営のパートナーであるなら、税務・会計はもちろん、中小企業経営の相談ができる相手を選ばなければなりません。
さらに、仮に税理士として税金の知識や経験に優れていたとしても、コミュニケーション面で税務や経営の相談を気軽にできなければ意味がありません。
そのため、まずは気軽に相談できるかどうかを決める第一印象や相性が、税理士選びの最重要ポイントです。
2.積極的に経営に関するサポートを行ってくれるか
税理士側からすれば、個人事業主や中小企業の経営に関するサポートなどを行う経営コンサルティングは、必ずしもすべての税理士が提供しているわけではありません。
これを考慮すれば、経営コンサルティングを提供している税理士はとても貴重です。
税理士が行える経営コンサルティング業務の具体例を以下に示します。
- 融資・資金調達支援
- 経営計画(ビジネスプラン)策定支援
- 資金繰り(キャッシュフロー)支援
- 売上・集客アップ支援
- 補助金・助成金支援
- その他
この内、経営計画(ビジネスプラン)策定支援は補助金の申請や金融機関などからの融資・資金調達にも通じるものです。
補助金の申請や融資・資金調達のためには、第三者に対し自社の経営計画(ビジネスプラン)を論理立てて説明する必要があるからです。
顧問税理士を選ぶ段階においては、そもそも税理士自身に経営の経験があるか、わかりやすく提案する能力があるかを意識しておくと良いでしょう。
いずれも経営コンサルタントに必要なスキルであり、満たしていれば経営者に多大な利益をもたらすサポートを行ってもらえる可能性が高いと考えられます。
3.必要な時にすぐに対応してくれるか(レスポンスの早さ)
税理士に何らかの相談をした時、または業務を依頼した時、すぐに対応してくれるかどうかは重要なポイントです。
例えば、税金に関するちょっとした質問で実際に返答が来たのは1週間後・・・
このような場合にはレスポンスが悪く、重要な時に経営判断に支障が出てしまいかねません。
顧問契約前にレスポンスの早さを見分ける1つの方法は、顧問料の見積りを依頼した時にその提案が早いかどうかなどです。
ただし、注意したいのは2月や3月などの税理士の繁忙期です。
たった1人で多くの顧問先を持つ税理士の場合、2月や3月は特に顧問先の決算や確定申告の対応に追われています。
その場合はどうしても対応が遅くなってしまうことがあります。
しかし、このような場合でも事前に返答が遅くなってしまう旨を伝えてくれるかどうかで見極めが可能でしょう。
4.節税について知識・経験をもとに具体的な提案をしてくれるか
実は、積極的に節税を提案しない税理士もいます。
なぜなら、税理士は本来税金を正しく納めることをサポートする立場だからです。
節税を期待して税理士との顧問契約を考えているのであれば、節税について具体的な提案をしてくれるかどうかも重要なポイントです。
節税方法は、業種によってまたは税制の改正によって変わります。
一度税理士に節税の相談をして、具体的な提案をしてくれるかどうか確認してみましょう。
5.顧問料・決算料など報酬料金の体系に明瞭性があるか
税理士に業務を依頼する場合にかかる費用は、「税理士報酬」または「顧問料」などと呼ばれます。
たとえば、月々の顧問料が安いからといってそれだけで選んでしまうと、後々で失敗の原因になってしまいます。
それは、税理士によって依頼できる業務の範囲が大きく異なるからです。
例えば、融資・資金調達の相談は、顧問料とは別料金で設定していることもあります。
後々で想定外の費用になってしまわないよう、税理士と顧問契約する際には顧問料とその業務範囲について、事前にしっかり確認しておきましょう。
具体例を以下に示します。
- 記帳代行や経理代行を利用する場合
- 税理士との定期的な面談の回数
- 相談対応してくれる人は誰か(代表税理士or担当の会計事務所職員)
- 税務調査に立ち会ってもらう場合
- 資金繰り・キャッシュフローの相談やサポート
- 融資・資金調達の相談やサポート
- 経営コンサルティング
依頼したい業務別の税理士費用の相場について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もあわせてご参照ください。
関連記事:【税理士費用の相場まとめ】依頼内容別の相場まとめ表あり!費用を抑えるポイントも紹介
6.経営に関する相談に対して具体的にサポートしてくれるか
節税対策と同じく、経営に関する相談は本来の税理士業務ではありません。
「税理士と顧問契約すれば、いろいろと経営相談できる・・・」
このように期待していても、顧問契約を締結した後にまったく経営サポートを受けられなかったという事態は避けるべきです。
そのため、もし経営に関する相談を望んでいるのであれば、以下のポイントをきちんと確認しておきましょう。
すべての税理士が必ずしも中小企業経営に富んでいるとはいえませんが、次のようなことで多少のアドバイスができることもあります。
- 財務体質の確認と強化の提案
- キャッシュを最大限残すための提案
- 補助金や助成金の申請サポート
- 資金調達(融資・投資)サポート
- 事業承継サポート
7.自社の業界・業種に関する知識や経験を有しているか
飲食業・美容サロン業・卸売業・IT業・建設業・不動産業など、税理士によって経験のある業界・業種は異なります。
税理士が自社の業界・業種に関する知識や経験を有しているのであれば、より具体的な節税提案や経営サポートを受けられるかもしれません。
事前に顧問契約を検討している税理士のWEBサイトなどから、顧問先に同業他社がいると安心できるかもしれません。
8.資金調達に強いか
資金調達についても税理士の本来の業務ではありません。
そのため、資金調達に強い税理士とそうではない税理士に大きく分かれてしまいます。
もし税理士に資金調達サポートを期待しているのであれば、事前に確認しておくことが重要です。
資金調達の方法は、主に次の2つです。
- 銀行融資
- 出資を受ける
もしIPO(新規株式上場)を目指しているのであれば、IPO実績のある税理士だと安心できます。
主に、中堅企業・大企業をメインとしている税理士・会計事務所が良いでしょう。
逆に、オーナー経営(外部からの出資は一切受けず、創業者などが経営の舵取りを行う経営スタイル)で収益性の高い会社や店舗を目指しているのであれば、中小零細企業の実情や経営課題を深く理解し、親身に提案などしてくれる税理士・会計事務所が良いでしょう。
9.決算対策に関して幅広い視点から提案を行ってくれるか
「4.節税について知識・経験をもとに具体的な提案をしてくれるか」と一部重複しますが、決算対策の片方の側面として、納税額を抑えるために行う節税対策があります。
そしてもう片方の側面として、銀行などの金融機関やベンチャーキャピタル・個人投資家から資金調達するための決算対策である、赤字から黒字にしたいという意味での決算対策もあります。
決算対策は決算の直前だけでは取れる手段が限られてしまうため、3ヶ月前程度から利益予測を行い、幅広い視点からさまざまな対策を検討しなければなりません。
そのため、決算直前に税理士を検討するのではなく、3ヶ月以上前からの相談をおすすめします。
そこで、幅広い視点から具体的な提案をもらえるかどうかをチェックしておきましょう。
10.役員報酬の金額設定に関する相談に具体的に対応してくれるか
多くの経営者が毎年悩むポイントが役員報酬の金額です。
なぜなら、役員報酬の配分は大きく納税額に関わるからです。
役員報酬を高額に設定すると法人税を減らせますが、個人にかかる所得税や住民税などが増えてしまいます。
逆に、役員報酬を低額に設定すると所得税や住民税を抑えられますが、法人税を減らせません。
このように、役員報酬の金額設定は節税に関わる重要事項です。
そのため、役員報酬の金額設定に対して具体的に対応してくれる税理士かどうかをチェックしておくことが重要です。
11.度重なる税制改正に追いついているか
税理士は、常に変わっていく税制を把握し、経営者のニーズに応じた最適な提案をしなければなりません。
しかし、税制改正は頻繁でかつ複雑です。
例えば、直近2年間を考慮しても次のような税制改正が行われました。
「税制改正の概要」は、財務省が案内を出しています。
- 個人事業者の事業承継税制の創設
- 事業用の小規模宅地特例の見直し
- イノベーション促進のための研究開発税制の見直し
- 中堅・中小企業による設備投資等の支援
- 電子帳簿及びスキャナ保存制度の見直し
- 投資や賃上げを促す措置
- 連結納税制度の見直し
- 5G導入促進税制の創設
- 電子帳簿保存制度の見直し
このような税制改正に追いついていなければ、経営者に最適な提案ができません。
そのため、税理士が税制改正にきちんと追いついているかどうかが重要です。
12.違法性のある脱税・粉飾決算を提案してこないか
最後のチェック項目です。
違法性のある脱税や粉飾決算を提案してくる税理士とは顧問契約しない方が良いでしょう。
脱税をしてしまうと重加算税が課され、節税どころではなくなってしまいます。
最悪の場合は、5年以下の懲役または罰金が科されます。
また、税理士の提案で脱税を実行したとしても、このようなペナルティを受けるのは納税者である経営者です。十分に注意しておきましょう。
税理士を選ぶ・契約するタイミング
税理士を選ぶ・契約するタイミングについて簡単に解説します。
結論から申し上げれば、早ければ早い方が良いです。
しかしながら、現実はそうではありません。
一般的に税理士とどのようなタイミングで顧問契約することが多いのかを紹介します。
- 消費税の課税事業者となる時(課税売上高が1,000万円を超えた時)
- 法人成りする時(会社設立時)
- 決算直前
- 融資・資金調達をしたい時
- 税務調査の対象になった時
基本的には、会社設立時もしくはその前の起業準備の段階から税理士に相談していただくことが理想です。
確定申告や決算の直前だとまとまった対応となり、税理士の繁忙期と重なることもあるので、避けたほうが無難といえます。
税理士の探し方
税理士はどうやって探せば良いのでしょうか。
「会計事務所白書」によれば、現在依頼している税理士などを知ったきっかけは次の通りでした。
- 家族・知人からの紹介(61.1%)
- 他士業からの紹介(20.7%)
- 地域コミュニティー(5.7%)
- インターネット検索など(5.2%)
- その他
つまり、紹介を受けた方が80%を超えており大多数でした。
一方で、友人や知人・取引先などから紹介を受けられる経営者がすべてではありません。
また、自分に合った顧問税理士をしっかりと見つけたい個人事業主や法人もしくは起業を検討している方も多いでしょう。
そのような場合には、インターネットで税理士を検索し、自分に合いそうな税理士・会計事務所に個別に問い合わせてみましょう。
なお、自分に最適な税理士を探す方法について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もあわせてご参照ください。
関連記事:税理士が教える自分に最適な税理士を探す方法。「最初に誰と出逢うか」で天と地の差がつきます!
また、税理士とのやり取りは電話や対面での打合せといったコミュニケーション手段が主流です。
しかし、現在ではZOOMやSkypeなどコミュニケーションツールが発達・普及しており、多少遠方の税理士でも顧問契約しやすくなっています。
税理士を変更する前に押さえておくべきポイント
残念ながら、税理士と顧問契約を結んだ後に税理士を変更する経営者もいます。
税理士を変更するのも経営者にとって重要な判断の1つです。
しかし、税理士を変更する前にきちんと押さえておくべきポイントがあります。
簡単に要点をまとめますので、ぜひ参考にしてください。
- 確定申告や決算直前は避けるべき
- 解約前に次の税理士を探しておくべき
- e-Taxのパスワードや預けたデータなどの引き継ぎを行う
- 契約期間を確認し、違約金が発生しないようにする
税理士変更をスムーズに進めるためのポイントを詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もあわせてご参照ください。
関連記事:税理士変更をスムーズに進めるためのポイント!変更理由やタイミングなど税理士が解説
まとめ:失敗しないためのポイントをしっかり押さえて、自社に合った税理士選びを!
本記事では、失敗しないための税理士選びのポイントを紹介しました。
自社に合った良い税理士と顧問契約を結ぶことで、税務や経理業務の負担と納税額を抑え、限りある貴重な経営資源を最適に配分できます。
さらに、税理士によっては融資・資金調達サポートや経営コンサルティングを提供しており、重要な経営のパートナーとして起業や中小企業経営を成功へ導いていくことが見込めます。
逆に税理士選びに失敗してしまうと、「依頼した業務を行ってくれない」「レスポンスが悪い」「決算申告の品質・精度が低い」などの不満を持つこともあります。
そこで、本記事で紹介したポイントを面談の時などに事前にチェックしておけば、自社に合った良い税理士を選ぶことができるでしょう。
ぜひチェックリストのように活用していただき、自社に合った税理士と良好な関係を築いてください。